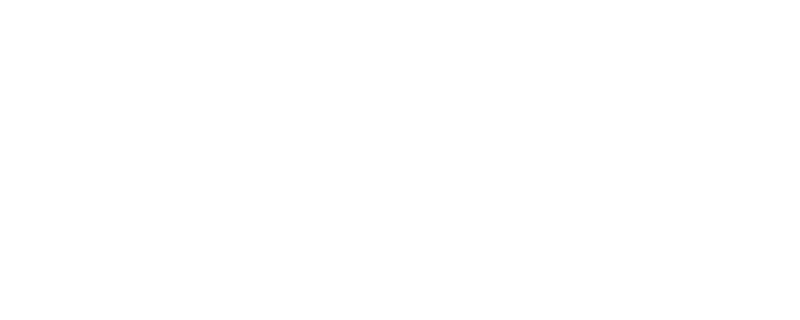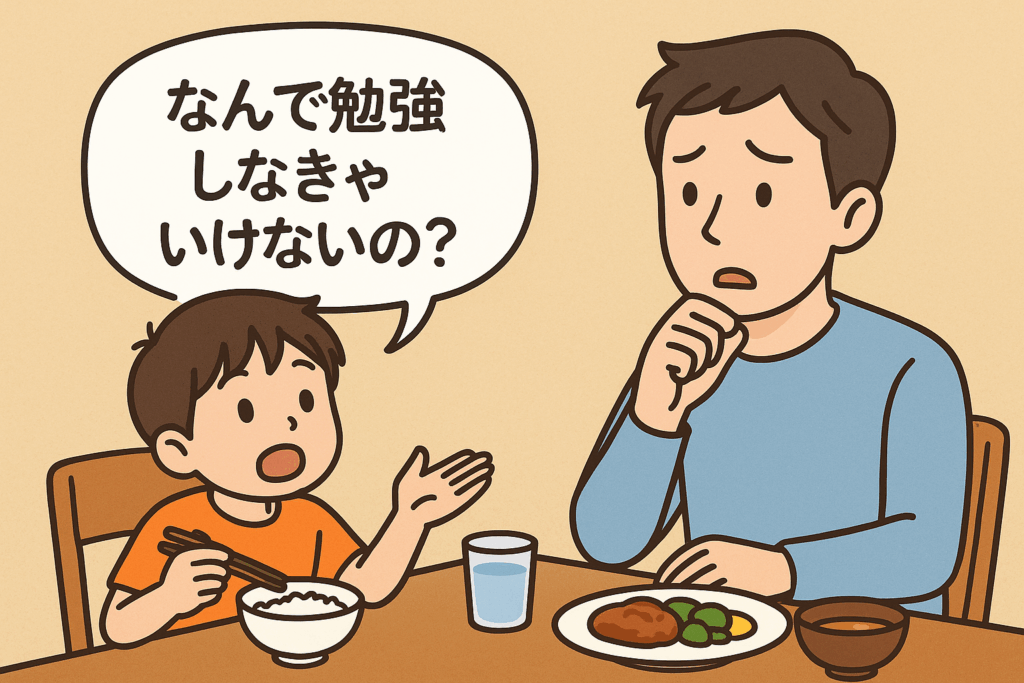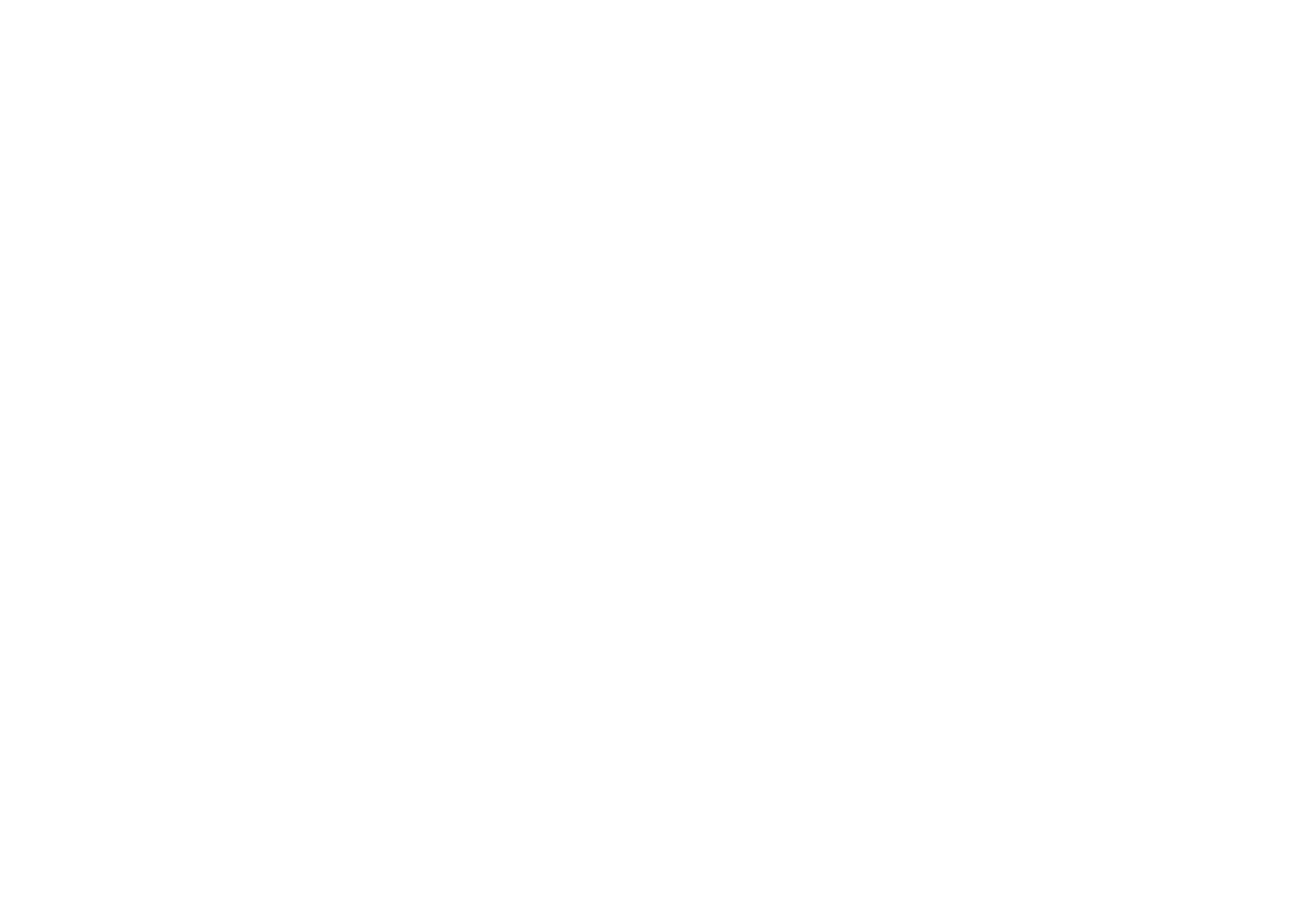子どもからの「なんで?」は、大人にとっても難問
こんにちは、整体師のフムロです。
今日は、息子からの質問にうまく答えられなかったお話。
夏休みも残すところあとわずか。
毎日の部活動と宿題、やりたかった科目の勉強の進み具合が計画通りにいかず「ヤバイ、ヤバイ」と独り言を連発している息子。
そんな息子から、
「なんで勉強しなあかんの?」夕食の最中、突然こんな質問が飛んできました。
不意打ちを受けた私は即答できず、思わず笑ってごまかしながら心の中で考えを巡らせました。
考えているうちに馴染みのある懐かしい想いがしました。そういえば、私自身も学生時代に何度も同じことを考えていました。
「勉強って、本当に必要なんかな?」っと。
勉強を避けてきた学生時代、そして社会に出てから気づいたこと
私は中学生からラグビーを始め、社会人になるまでずっとスポーツで進学してきました。
勉強が得意ではなかったことを苦に思ったことはありませんでしたが、社会に出てからその必要性を痛感する場面が少なくありませんでした。
仕事内容そのものに学校の勉強が直結することは少なくても、
- 上司やお客様との会話
- 一般的な教養を求められる場面
- 道を変えようとする時に立ちはだかる筆記試験
など、こうした場面で「基礎学力」が大きな土台になることを知ったのです。
勉強ができるかどうかではなく、「人生を自分で選びやすくするための力」として必要なんだと。
だから息子にはこう答えました。
「人生を主体的に選んでいけるようにするために、勉強は大事なんやと思うよ」
ただ少し抽象的すぎたのか、息子は首をかしげたまま。その顔がなんだかおかしくて、思わず笑ってしまいました。
すべての教科は、コップの水ひとつから広がっていく

その夜、布団に入りながら「もっと伝わりやすい言葉はなかったのかなぁ」と考えていると、以前SNSで目にした投稿を思い出しました。
それは「コップの水」を例にした、とても分かりやすい答え方でした。
お母さんが息子に、机の上に置いたコップを指さしながら、こんな風に話していくのです。
- 算数を学べば、この中に200mlの水があると数字で見えるようになる
- 理科を学べば、この水が酸素と水素からできていると知ることができる
- 社会を学べば、この水がどこから来たのかが分かり、そして世界にはこの綺麗な水を飲むことができない人たちがいることもわかる
- 美術を学べば、この水の反射を綺麗に描くことができるようになる
- 音楽を学べば、同じコップでも水の量で音を変えられることにも気づける
- 技術を学べば、コップがどんな素材ででき、なぜ漏れないのかが分かり、人の創造力の凄さを知ることができる
- 保健体育を学べば、この水がどれだけ大切なのか、健康を支える命の正体が見えてくる
- 道徳を学べば、この水を誰かと分け合うことの大切さを学び、思いやりの心が育つ
- 国語を学べば、今話した全部の意味を正しく理解できるようになる
- 英語を学べば、この話を世界中の人と共有し分かち合えるようになる
- 哲学を学べば、そもそも「この話にどんな意味があるのか」と考えられるようになる
すべての学びが、コップの水ひとつからつながり、広がっていく。
私はこの話を思い出し、「あぁ、こう伝えれば良かったな」と感じたと同時に的を得ない回答をしてしまったと恥ずかしくなりました。
「なぜ?」にどう答えるかで、学びの意味が深まる
子どもが小さい頃、3歳から5歳くらいまでは「なんで?」「どうして?」と質問攻めにされる日々でした。
いま思うと、その時の私は、答えが的外れなことも多かったかもしれません。
けれども、子どもの「なぜ?」には、できる限り真剣に答えたい。
そうやって向き合うことで、学びの意味も、親子の対話も、少しずつ深まっていくのだと思います。
最後に、この記事を読んでくださったあなたにも問いかけたいのです。
もし子どもや誰かに「なんで勉強しなきゃいけないの?」と聞かれたら、あなたはどんなふうに答えますか?